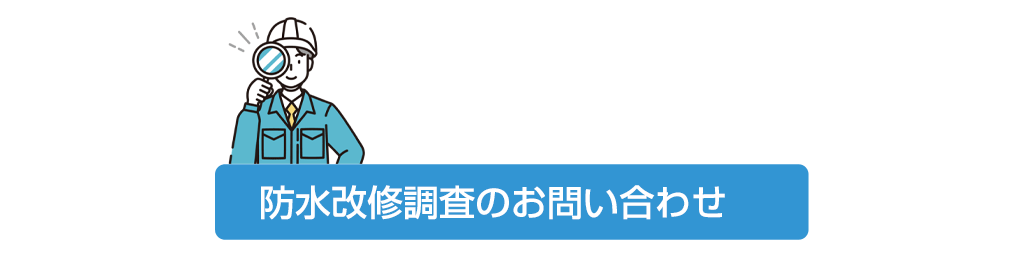屋上緑化の効果は環境にやさしいだけじゃない!注意点と対策、補助金制度も紹介

屋上緑化は、ヒートアイランド現象の緩和や省エネルギー効果など、環境面でのメリットが注目されがちですが、じつは建物の保護や資産価値の向上にも貢献します。
しかし、施工コストや防水層への影響、メンテナンスの負担など、導入前に知っておくべき注意点も。
本記事では、屋上緑化がもたらす多様な効果と、失敗しないための対策、活用できる補助金制度までくわしく解説し、導入にお悩みの建物管理者をサポートします。
コラムのポイント
・耐風性の高い植物選定や軽量土壌の採用、排水システムの整備により、安全で長持ちする屋上緑化を実現できます。
・国や地方自治体の補助金制度で、初期費用の負担を軽減しながら屋上緑化の導入が可能です。
屋上緑化とは

屋上緑化とは、建物の屋根や屋上に植物を植えて、緑地として活用する取り組みを指します。
都市部では、コンクリートやアスファルトで地面が覆われ、気温が周囲よりも高くなる「ヒートアイランド現象」が起きています。
緩和や都市環境の改善を目指し、工場・倉庫・車庫、商業施設など、民間での導入事例が増加中です。
最近では、より環境に配慮した取り組みとして、植栽基盤の厚みを持たせる工法の採用が増えています。
中高木などの多様な植物を長期的に育てられ、地域の緑地と調和した豊かな景観づくりや、生物多様性の確保にもつながっています。
屋上緑化の効果

屋上緑化は、環境問題への貢献から建物の保護、住む人の心身の健康に至るまで、さまざまな効果が期待できます。
ヒートアイランド現象を緩和する
屋上緑化がヒートアイランド現象を抑えるのは、植物の持つ高い保水力のおかげです。
草地や森林は、アスファルトやコンクリートと比べて水を多く蓄えます。
水分が蒸発するときに、周りの熱を奪うため、地表面から大気へ伝わる熱が少なくなり、主に日中の気温の上昇を抑える効果が生まれます。
参考:気象庁|ヒートアイランド現象とはどのようなものですか?
遮熱・省エネルギー効果がある
屋上緑化は植物の水分が蒸発する際に熱を奪い、夏場は建物にとって「緑の日傘」のような役割を果たしてくれます。
この恩恵を受けるのは、屋上直下のフロアです。
植栽が太陽の光を遮り、さらに断熱効果をもたらすことで、植物の蒸散作用とあわせて、建物の熱環境を改善します。
冷房や暖房の効率向上は光熱費の削減に直結するため、省エネルギー効果が期待できます。
CO2を削減する
屋上緑化の植物は、光合成によって空気中のCO2を吸収します。
都市部の空気の質を改善する、環境にやさしい取り組みにつながりです。
建物を保護し、劣化を遅らせる
露出した屋上では、夏場の昼夜で30℃以上の温度差が生じる日もあります。
温度差によるコンクリートの膨張と収縮は、建物の劣化を招く原因です。
屋上緑化は温度変化を緩和し、緑化された層が建物の防水層や構造体を保護する役割を果たします。
さらに、紫外線も遮断してくれるため、建物の耐久性が向上し、結果として長期的な修繕費の削減にも役立ちます。
雨水の流出を抑える
屋上緑化システムには保水効果があるため、ゲリラ豪雨などで屋上の雨水がいっきに流れ出すのを遅らせられます。
雨水が一時的に貯留されることで、下水や河川への急激な流入が抑制され、都市型水害を軽減する大切な役割を担っています。
リラックス効果がある
緑という自然の色は、人の心を癒し、安らぎを与える効果があると言われています。
ストレスを感じやすい都市生活を送る方にとって、屋上緑化がもたらす景観の向上は、数値では表せない心理的なメリットです。
また、環境に配慮した取り組みとして、企業のイメージアップにつながる効果も期待できます。
建物活用の幅が広がる
従来、単なるオープンスペースであった屋上に植物を植えることで、憩いや癒しの場といった新たな価値を持つ空間が生まれます。
自治体による緑化の義務付けに対応するだけでなく、居住者や利用者のためのコミュニティスペース、または新たな経済活動の場としての可能性も秘めています。
屋上緑化の注意点と対策

屋上緑化の導入は、メリットだけでなく、注意すべき点もあります。
施工や維持にコストがかかる
屋上緑化は、システムを導入する初期費用だけでなく、長期にわたって維持管理するための費用も発生します。
代表的な維持管理には、植栽の剪定・枯葉の除去・水やり(灌水設備の設置)・雑草対策・害虫対策などが含まれます。
対策|コスト削減できるシステムを選ぶ
簡易的な薄層型システムの採用で、庭園型に比べて初期費用を抑えられます。
また、国や地方自治体の緑化関連の助成金制度を活用することで、導入コストの軽減が可能です。
水やりや除草といった維持管理には年間で一定の費用がかかります。
建物の劣化や漏水リスクを防ぐためにも、専門業者による年間管理を委託し、費用を建物運営の必須経費として予算に組み込むのが安心です。
屋上緑化では、土壌や枯葉によるドレンの詰まりにとくに注意が必要です。
屋上ドレンのトラブルと対策について、こちらの記事もあわせてご覧ください。
適切な植物選びと風対策が必要
屋上は地上と比べて風の影響を強く受けやすく、植栽の健全な育成や安全性の確保に配慮が必要です。
強風による植物の乾燥・枝折れ・土の流出・高木を植えた場合の倒木リスクを考慮しなければなりません。
対策|耐風性の高い植物選定と植栽の固定
屋上の厳しい環境に耐えられる、耐風性や乾燥耐性の高い植物を選定しましょう。
とくに高木を植える際は、適切な根鉢の固定や支柱による補強が必要です。
軽量化が求められる薄層型などのシステムは、土壌が限られているため、乾燥に強いセダム類やハーブ類が一般的です。
屋上の耐荷重が必要
土壌や植栽、さらに雨水を含んだ状態の重量は、建物の構造に大きな負荷をかけます。
事前に構造計算を行い、建物の耐荷重を確認することが不可欠です。
既存の建物に導入する場合、湿潤状態の土壌重量が建物の耐荷重制限を超えてしまうリスクがあるため注意が必要です。
対策|構造設計の確認と軽量化技術の採用
建物の構造設計を確認し、必要に応じて従来の黒土よりも軽い人工軽量土壌や、ゼオライトなどの軽量化技術を採用することで、建物の負担を軽減できます。
一般的な屋上よりも雨漏りへの配慮が必要
緑化層は建物の防水層を保護する効果がある一方で、排水がうまくいかないと漏水事故につながる可能性があります。
排水不良により緑化層内で水の滞留や排水口の詰まりが発生し、漏水を招く危険性があります。
対策|適切な防水層設計と排水システムの整備
防水工事を万全に行ったうえで、排水層・排水管・ルーフドレイン・化粧側溝などを適切に設置し、排水を促す設計が大切です。
また、植物の根が防水層や接合部を突き破り、漏水を引き起こすリスクもあります。
ボックス型システムの採用や耐根シートの採用で、根の侵入・貫通を防げます。
屋上緑化に活用できる補助金制度

屋上緑化の導入には、国や地方自治体が提供する補助金制度の活用で、初期費用の負担を軽減できます。
制度の内容は自治体や年度によって異なるため、最新情報はお住まいの自治体にご確認ください。
| 制度名 | 補助対象 | 補助額・補助率 | 申請期間 |
|---|---|---|---|
| 国土交通省|防災・省エネまちづくり緊急促進事業 | 以下の要件を満たした上で、都市緑化が対象になる 【必須要件】 ・バリアフリー化 ・子育て対策 ・防災対策 ・省エネルギー対策 ・環境対策 |
・必須要件のみに該当する場合: 3%
・必須要件 + 選択要件の2項目に該当する場合: 5%
・必須要件 + 選択要件の3項目(以上)に該当する場合: 7%
|
令和12年3月31日までに着手した事業が補助対象 |
| 千代田区|ヒートアイランド対策助成 | 屋上緑化、壁面緑化、敷地内緑化など | 助成対象経費の50%(上限200万円) | 令和8年2月13日 |
屋上緑化の効果Q&A

お客様の疑問を解決し、より深く屋上緑化について理解していただけるよう、よくあるご質問にお答えします。
Q. 屋上緑化のメンテナンスは具体的に何をする?
屋上緑化のメンテナンスは、緑化システムのタイプや植えている植物によって異なります。
主に必要となるのは、植物が健康に育つための「水やり」や「肥料やり」です。
また、景観を保ち風通しを良くするための「剪定」、意図しない植物が生えるのを防ぐ「除草」、病害虫の発生を防ぐための「害虫対策」などがあります。
とくに、排水口周りの落ち葉やゴミを取り除く「清掃」は、漏水リスクを減らすために欠かせません。
専門業者に管理を委託すると、これらの作業を定期的に行ってもらえるため安心です。
Q. 屋上緑化による防水層への影響はありますか?
屋上緑化は、適切に施工されていれば、むしろ防水層を保護する役割を果たします。
直射日光の紫外線や、昼夜の急激な温度変化から防水層を守ってくれるため、防水層の劣化を遅らせ、建物の耐久性を向上させることも可能です。
しかし、植物の根が防水層を突き破る「根の侵入」による漏水リスクがあります。
根の侵入を防ぐ「耐根シート」の採用、システム全体が防水層と分離している「ボックス型システム」を採用するなどの対策が必要です。
Q. 屋上緑化の防水層の改修はどのように行えば良いですか?
植栽を残置したままで、非植栽部を改修すると部分補修とみなされてしまうため、根本的な防水改修を施すには、屋上緑化を全て撤去する必要があります。
通常の防水改修サイクルに従い、このような撤去を繰り返すのは、居住者や近隣だけでなく、環境へも負担をかけます。
屋上緑化を全面に施し、防水層をくまなく覆うことで、耐用年数の延命を図ったり、高耐久防水(露出仕様で45年、保護仕様で80年)を採用するなど、改修頻度の軽減措置がおすすめです。
関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。
当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計191社の正会員がおります(2025年10月時点)。
また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。
「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。
当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。