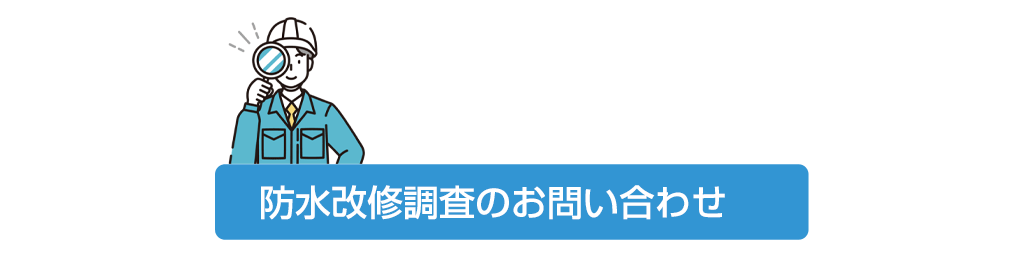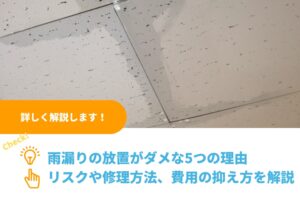建物の長寿命化のメリットや流れとは|サステナブルに欠かせない「高耐久防水」も解説

建物の長寿命化は、ライフサイクルコストの削減や資産価値の向上、環境負荷軽減によるSDGsへの貢献も実現できるため、改修工事を検討している方から注目されています。
しかし、必要な工事や流れがわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、建物を長寿命化する4つのメリットから実際の進め方まで、建物を管理している方が知っておくべき情報を詳しく解説します。
長寿命化に欠かせない防水改修について、サステナブルな「高耐久防水」をご紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。
・防水改修は雨漏りによる建物全体の劣化を防ぐために欠かせない工程です。
・30年耐用の「ガムクールFRAT」は従来の10~15年サイクルを延長し、太陽光パネル対応でサステナブルな防水を実現します。
Contents
建物の長寿命化とは|サステナブルに必要な考え方

建物の長寿命化とは、建築物を適切にメンテナンスし、機能と価値を長期間にわたって維持する取り組みです。
従来の「建てては壊す」というスクラップ&ビルドの考え方から「長期にわたって使い続ける」ストック活用型への転換を意味します。
建物の長寿命化には、計画的なメンテナンスと適切な改修工事が不可欠です。
また、長寿命化を意識した設計や材料選びにより、より効率的に建物を管理できます。
近年では、環境負荷の削減と経済効率の向上を両立する手法として、多くの企業や自治体が建物の長寿命化に取り組んでいます。
建物を長寿命化する4つのメリット

建物の長寿命化により得られるメリットは多岐にわたります。
ライフサイクルコストの削減
建物の長寿命化により、建物の生涯にかかる総費用を削減できます。
- 設備の更新時期に合わせた効率的な工事計画で、費用削減と稼働率向上を実現する
- 長期修繕計画に基づいた資金計画で、修繕費用を平準化できる
環境負荷の低減
建物の長寿命化は、建設業界における環境負荷削減の有効な手段です。
- 建物の解体・新築に伴う廃棄物の発生量を削減し、新たな建設資材の使用量も抑える
- 建設に関わるCO2排出量を削減する
- 長期間の使用で、建設時のエネルギーや資源を有効活用できる
不動産としての資産価値の向上
適切な維持管理により、建物の資産価値を長期間維持できます。
また、計画的な改修工事により、建物の機能性や快適性を向上させ、市場価値の向上も期待できます。
- 定期的なメンテナンスで、満足度向上と空室率の低下につなげられる
- 長期修繕計画で将来の修繕費用が明確になり、金融機関からの信頼も得やすい
- 建物の履歴管理により、売却時の査定においても有利に働きやすい
建物の安全性・災害対策の強化
長寿命化の取り組みにより、建物の安全性を継続的に向上できます。
- 定期的な建物診断により、構造体の劣化や不具合を早期発見し、適切な対策をとる
- 耐震性能の向上工事や防災設備の更新により、災害に負けない建物になる
これらの取り組みにより、利用者の安全確保と建物の持続的な運営が可能です。
建物長寿命化の流れ

建物の長寿命化を効率的に進めるための基本的な流れを、4つのステップに分けて解説します。
ステップ1|建物診断で現状を把握する
建物の長寿命化を始める前に、現在の建物状況を正確に把握しましょう。
専門家による建物診断では、構造躯体・外装・内装・設備など、建物のあらゆる部分について調査を実施します。
劣化の程度や進行状況、安全性に関わる問題点などを明確にできるだけでなく、修繕計画の策定における根拠資料としても活用可能です。
建物調査が欠かせない理由について、こちらで詳しく解説しています。
ステップ2|長期修繕計画の作成
建物診断の結果を基に「今後10年〜30年程度の期間において、どの部位をいつ修繕するか」を明確にした長期修繕計画を策定します。
計画には各修繕工事の概算費用と実施時期を記載し、資金計画の立案にも活用可能です。
長期修繕計画は定期的に見直しを行い、建物の状況変化に合わせて更新します。
長期修繕計画が大切な理由や活用方法について、こちらで解説しています。
ステップ3|給排水・電気・空調設備の計画的な更新
建物設備の適切な更新は、快適性と機能性の維持に欠かせません。
設備の老朽化を放置すると、さまざまな問題を引き起こします。
- 給排水設備:配管の腐食や詰まりが漏水・断水を引き起こす
- 電気設備:劣化は停電や火災発生の原因になる
- 空調設備:室内環境の悪化を招くだけでなく、予期せぬ修理費につながる
設備の更新時期は、機器の耐用年数と故障履歴を参考に決定します。
計画的な設備更新により、突発的な故障による影響を抑えられます。
ステップ4|屋上・外壁の防水改修

屋上防水の劣化は、雨漏りによる腐食や内装のダメージを引き起こすため、建物の耐久性に直結します。
防水改修の方法には以下の2つがあり、既存防水層の状態に適した改修方法を選択します。
- 被せ工法:既存防水層の上に新しい防水層を施工
- 撤去工法:既存防水層を撤去して新設
高耐久性の防水材料を使用することで、次回の改修時期を延ばし、ライフサイクルコストの削減も可能です。
サステナブルと長寿命化を「高耐久防水」で叶える
建物の長寿命化を考える上で、屋上防水は非常に重要なポイントです。
近年、建物の価値向上を目的とした屋上活用が進んでおり、特に太陽光パネル設置を見据えた屋上改修の検討が増加しています。
これに伴い、屋上防水には防水層の高耐久化へのニーズに対応できる性能が求められるようになりました。
このような時代の要請に応え、建物の長寿命化と環境負荷の軽減を実現する防水工法が、改質アスファルトシートに塗膜防水を併用する高耐久防水「ガムクールFRAT」です。
ガムクールFRATは、防水性能を約30年間維持できます。
そのため、太陽光パネルと同時に施工すれば、防水層の改修工事は30年後となり、太陽光パネルを一度も撤去することなくフル稼働させることが可能です。
また、保護コンクリートの打設なしで高耐久化を実現できるため、工期短縮による省力化や、製造・運搬に伴うCO2排出量の削減にもつながります。
改修工事をご検討の際は、建物の価値向上だけでなく、環境への取り組みにも貢献する「高耐久防水」を選択肢に加えてみませんか?
「高耐久防水を採用したい」「どんなことができるのか?」「まずは建物の状態を知りたい」など、屋上改修に関するお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。
関防協は、防水工事の「エキスパート集団」です。

工事会社を選ぶのに不安を感じる方は、ぜひ関東防水管理事業協同組合(関防協)へまずはお気軽にご相談ください。
当協同組合は、主に関東にある防水改修の会社で形成されているグループで、東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬の関東地域に限らず、山梨・静岡・長野・新潟にも支部があり、計190社の正会員がおります(2025年6月時点)。
また、年々進化し続けている防水工事についての教育活動も行なっており、適切な調査や提案ができる「防水改修調査診断員」の育成を実施しています。
「雨漏り診断をどこに依頼すれば分からない」「信頼できる施工会社の選び方が分からない」そんな方は関東防水管理事業協同組合へご相談ください。
当HPでは、防水改修調査診断員による無料診断も申し込みや、マップ上での施工店検索ができます。 少しでも防水に不安や不満を感じている方は、ぜひお気軽にご相談ください。